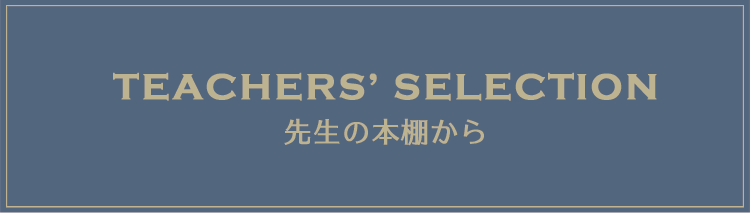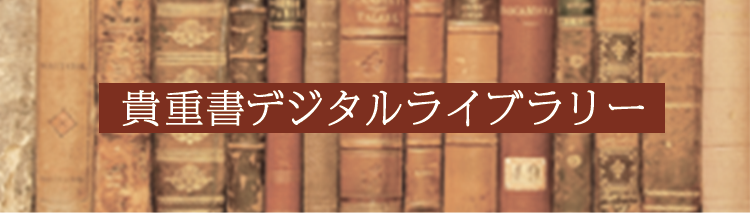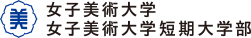第26回女子美パリ賞受賞者 朝倉優佳
4月18日
はじめて、スーパーマーケットで店員さんに話しかけてみた。
私は、どんなに些細なことでもフランスでの生活における「はじめて」の経験は、必ず手帳に書き記すことにしている。当たり前にできることを、あえて言葉で残すことで、それを自覚的に認識しようと努めているのだ。一見、馬鹿馬鹿しい作業のようにも思えるが、これが生活もしくは制作のための土壌をつくるうえで、案外大切なことだったりする。
私は以前ドイツに住んでいたとき、移りはじめの頃は生活と制作のバランスが取れず、落ち着かない気持ちでいた。慣れないことの連続で、生活の基盤を整えるのに思っていた以上の時間と労力を要したためだ。生活が整わなければ、当然ながら制作に集中するための環境も整いにくい。外国語に囲まれることにも慣れておらず、思うように動けない自分へのいらだちや、言葉へのプレッシャーが重なり、やりたいこととやれることのバランスが取れるようになるまで、半年近くかかった記憶がある。
今回も同じようなことが起こり得るだろう、と予感していた。私は再び新しい言語に触れ、異なる文化の中に身を置きながら活動しようとしているからだ。実際、今の私はまるで幼児のようなものだ。買い物ひとつ取っても、言葉はたどたどしく、量り売りや自動精算機の仕組みもまだよく理解しておらず、何をするにも頼りない状態である。
そこで、私はできないことに、自身の生活の不完全さばかりに目を向けるのではなく、その日行なった些細なことに注目してみることにした。その方がずっと楽しいし、一日のなかで大きなことはしようとせず、小さな生活の中に喜びを感じることができれば、制作へも落ち着いて気持ちを向けることができる。そして少しずつ制作に向かう時間がとれるようになれば、集中力の密度も増していくだろう。小さな達成に目を向ける心持ちが新しい環境での生活では役立つ。これはドイツ留学時代に得た教訓である。
この日は電子レンジ内を掃除するための道具を求め、スーパーに来た。
「ビネガーはどこにありますか?掃除用の物を探しているんです。」
フランスに長く住む友人曰く、しつこい汚れを落とすにはホワイトビネガーを使うらしい。初老の店員さんは、棚に商品を並べていた手を止め、いぶかしげな顔でこちらを見た。
「食用はあそこにあるけど掃除用?Lavabo(洗面台)を洗うやつかい?」
そのとき私は、電子レンジをフランス語で何と言うか頭に入れてなかったことに気づき、必死に「えーっと、それだけではなくて…」と、ムニャムニャ伝えようとすると、「あぁ、それなら上の階にあるよ。○○っていうんだ。いいかい、○○だよ。」
肝心の○○のところが聞き取れない。とりあえずこの階ではなく、上の階にあることがわかった。これは大きなヒントだ。
今の私にはこれで十分成功である。予想以上に丁寧に、笑顔で教えてくれた店員さんにお礼を言い、上の階で無事探していたものを見つけ、購入することができた。今日の「はじめて」を見つけることができた。
“As soon as possible”
日常と非日常は、決して完全な対極にあるわけではない。両者は、ほんの少しのズレを伴いながら重なり合っているように感じる。たとえば、「時間との付き合い方」がそのひとつだ。
パリの朝焼けや夕焼けは、東京のそれと比べると、ほんの一瞬の出来事である。東京では、晴れていれば朝7時ごろには空が明るくなり、昼から14時ごろにかけて陽射しが最も強い。そこから太陽はなだらかに傾いて、夕焼けの時間もたっぷり取ったあと、ゆっくりと沈んでいく。
一方でパリでは、朝焼けのような柔らかい光の時間はほんのわずかで、すぐに日中の顔になる。今の季節であれば、夜21時ごろまで青空が広がり、明るいままだ。気温のピークは17時ごろ。夕焼けが見えるのは、太陽が沈む直前のほんのひとときだけである。
私は日本では、朝7時頃から仕事を始め、昼頃にはその日の仕事のほとんどを終わらせ、手を動かす時間より見る時間を増やしていく。午前中は心のゆくまま手を動かし、午後には鑑賞者の目線を取り込みながら、少ない手数で質のある仕事をする—というのが理想で、実際はそんな充実した内容には滅多にならないのだが—スケジュール自体はこんな感じである。集中力は時間と共に鋭くなるが、判断には朝が一番適していると思っている。
今は、フランスにおける制作に適した時間帯を探っているところだ。私の作業部屋は南東向きで、天気の良い日には昼前から強烈な光線が差し込んでくる。かと思えば、雲がすっと横切って、突然部屋が暗くなることもある。時間と同時に光との付き合い方もまた、重要になりそうだ。
この日は制作の合間にコインランドリーへ洗濯物を持っていった。施設内には6台の洗濯機があるが、数日前に覗いたときには、そのうち3台が故障していた。貼り紙には「なるべく早く対応します」とある。
この施設には200人以上が滞在しており、洗濯機は常に取り合い状態だ。しかも、乾燥機は1台しかない。洗濯に来る度にそこに居合わせた者同士で洗濯機の不便さについて話すのがお決まりのようになっている。
この日、コインランドリーを覗くと、故障中の洗濯機は6台中5台に増えていた。これにはむしろ笑ってしまった。
ここでの「なるべく早く」はだいぶ違うようだ。
多民族のなかの個
アジア人であるということはどういったことだろうか。とくにアジアから離れた、異なる文化圏に身を置いたとき、多くの人が一度は向き合う問いではないだろうか。アジア人に対する差別――それにどう向き合い、どう受け止めるか。
自分がアジア人であることを意識する場面は多い。たとえば、見た目、母国語、家族がいる地理的背景、そういったさまざまな要素を通して、私たちは自分の「出自」(「自分たちがどこから来たのか」ということ)を自覚する。ときに強く、無意識のうちに。
パリという街にいると、ふとした言語や振る舞いのなかで「自分がアジア人であること」を痛感させられることがある。一方で、多民族の行き交う街であるがゆえに、自分がこの人々の中に溶けこんでいて、自身の姿形がどういったものだったか忘れそうになることもあり、たまに店舗の窓に映り込む自分の姿を確認すると「すごくアジアらしいな」と小さく驚いたりもする。
買い物をする時、何かしらの手続きを行う時、差別的な対応を受けたことはそれなりにある。街の景色の一部となっている時はアジア人として何かしらのイメージを一方的に付与されることがあるようだ。しかし興味深いのは、個人として向き合った相手––ある程度の人間関係を築いた人間から差別的な言動を受けた記憶はあまりない。これはどういうことだろうか。
もちろん、文化に対する誤解や無意識の偏見が、差別的な表現として現われることはあるが、人間関係の中で、会話を重ね、訂正し合い、友人としてのやり取りの中で着地する場所を見出せてきた気がする。そして、それでもなお生じる軋轢があるとすれば、それは「差別」というより、「人間関係の問題」だと感じる。
差別に対して声を上げる人が多くいることは重要だ。それは、過去も現在も、差別によって傷つき、苦しんできた人々にとって、大きな励ましであり、必要な連帯でもある。ただ、ヨーロッパのすべての人々に、「アジア人に優しくあってほしい」と願うことは、現実としては難しいと感じざるを得ない。差別の背景にあるものや、その温度は、個人ごとに異なるからだ。アジア人全員が「善良」であるわけでもなく、それは他のどの民族についても同じだ。
だからこそ、私たちは「個人」として認識されるべきなのだと思う。
どこの国のパスポートを持っているか、どの言語を話すかは、その人を形づくる一部ではあるが、それが全てではない。私たちが他者からどう認識されたいのか、そのイメージを自らつくっていく姿勢が必要ではないだろうか。
逆に、「日本人であること」「アジア人であること」にすがり、そこに執着する人ほど、他の民族に対して無意識に差別的な思考を抱きがちのように感じる。「個」としての自立がなければ、人は自らのルーツという集団に固執し閉じこもるしかなくなる。そして、そうした集団が膨れ上がれば、それは民族主義というより、排他的な差別主義に変わっていってしまう危うさすらある。
だからこそ、私たちは慎重でありたい。他者と「個人」として向き合う強さと、差別や誤解に対して丁寧に応答できる柔軟さと、笑うことを忘れない辛抱強さを。私は持ち続けたいと思う。




2025年10月2日